(前ページ スヴャトスラフ・リヒテル EMIレコーディングス(3) はこちら)
巨人リヒテルの本領発揮~協奏曲録音集~
Disc 09
モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K.482
リッカルド・ムーティ(指揮)フィルハーモニア管弦楽団
録音:1979年
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37
リッカルド・ムーティ(指揮)フィルハーモニア管弦楽団
録音:1977年
Disc 10
ベートーヴェン:三重協奏曲ハ長調Op.56
ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1969年
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第4番イ短調Op.23
オレグ・カガン(ヴァイオリン)
録音:1976年
Disc 11
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83
ロリン・マゼール(指揮)パリ管弦楽団
録音:1969年
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ト長調K.379
オレグ・カガン(ヴァイオリン)
録音:1974年
Disc 12
ドヴォルザーク:ピアノ協奏曲ト短調Op.33
カルロス・クライバー(指揮)バイエルン国立管弦楽団
録音:1976年
バルトーク:ピアノ協奏曲第2番Sz.83
ロリン・マゼール(指揮)パリ管弦楽団
録音:1969年
Disc 13
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16
シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指揮)モンテ・カルロ国立歌劇場管弦楽団
録音:1974年
Disc 14
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第5番ト長調Op.55
ロリン・マゼール(指揮)ロンドン交響楽団
録音:1970年
ベルク:室内協奏曲
オレグ・カガン(ヴァイオリン)
ユーリ・ニコライエフスキー(指揮)モスクワ音楽院器楽アンサンブル
録音:1977年
大ピアニスト、スヴャトスラフ・リヒテルは生前、ピアノ独奏、室内楽において卓越した手腕をみせてくれましたが、彼が最もその恐るべき実力を発揮したのは、協奏曲のジャンルでした。
西欧デビュー時にドイツ・グラモフォンに遺したラフマニノフとチャイコフスキーも「超」の字がつく名演でしたが、このEMIボックスに収められた協奏曲集もまた、天下の名盤と呼ぶにふさわしいものばかりです。
ベートーヴェンの三重協奏曲と言いますと、わが国を代表する音楽評論家であった吉田秀和氏が、「駄作!」とはっきり書いた作品として知られます。確かに、楽聖の充実した5曲のピアノ協奏曲なんかに比べると、魅力や技術の面で少し足りないような印象も受けますが、それでも第1楽章の雄大さ、楽器の魅力を最大限に引き出した音色の多彩さを聴けば、「駄作」の評価はあまりにも見当違いだ、と言わざるを得ません。。
ところで、このような地味な曲に目を付け、商業的に大成功を収めた名盤があります。
それは、EMIが1969年にオイストラフ、ロストロポーヴィチ、リヒテルというソ連の3巨人をソリストに招き、西側のスーパースター、カラヤンとベルリン・フィルに伴奏させた、衝撃的なディスクです。
他にも、EMIは冷戦中の東ドイツにカラヤンを派遣し、ドレスデン・シュターツカペレとワーグナーの「ニュルンベルクの名歌手」をレコーディングさせるなど、この時期、共産圏とかなり野心的なプロジェクトを成功させています。
それにしても、三重協奏曲の素晴らしさはたとえようがありません。冒頭からカラヤン・サウンド全開の、ズシリと重く、色彩豊かなオーケストラの響きが眼前に広がります。そして、チェロ、ヴァイオリン、ピアノが千両役者の如く一人ずつ現れるさまはまさに鳥肌もの!
それからは、まさに「がっぷり四つ」という言葉がふさわしく、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲、ピアノ三重奏曲、交響曲が次々と現れるような音楽になっています。凄い!
とにかくロストロポーヴィチのチェロが朗々と鳴り響き、表現も雄弁。オイストラフのヴァイオリンは研ぎ澄まされたような美しさが光り、さらにリヒテルの珠を転がすような美しいピアノにも聴き手は惹きつけられます。
第2楽章ラルゴは、もう音のご馳走というべきでしょうか。元々が甘美な音楽ですが、3人のソリストが夢見るような音色と歌に満ちた音楽を繰り広げ、いつまでも聴いていたいという気持ちにさせられます。
フィナーレは圧巻。ここで聴くオイストラフのテクニックの冴えが尋常ではありません。中間部は短い音の連続ですが、快刀乱麻、切り込み鋭いヴァイオリンを主役に立て、スケール豊かにクライマックスへ向かっていきます。
やはりこれだけの名手が揃うと、どんな曲だってものすごい聴きごたえのする音楽になることを示した名盤と言えるでしょう。
クライバーとのドヴォルザーク
これまた知る人ぞ知る音楽です。ポピュラーな名曲を次々と生み出したドヴォルザークの作品の中でも、普段は演奏されることが非常に珍しいピアノ協奏曲。それを巨匠リヒテルと新進気鋭の若手、カルロス・クライバーがコンビを組み、世に送り出しました。
ちょっと極端な表現ですが、このディスクによって当曲は有名になった、と言ってもよいかもしれません。いくらリヒテルでも、ドヴォルザークの「ピアノ協奏曲」一本でヒットを飛ばすのは至難の業でしょうが、伴奏にあの録音嫌いのクライバーを引っ張り出したことで、このディスクはロングセラー商品になっています。
第1楽章から重厚なオーケストラパート。クライバーはピアノに遠慮することなく、オーケストラを呑み込むような巨大な音楽を創り上げ、弦楽器をうねらせます。まるで、ブラームスの交響曲のように聴こえるところがユニークです。
最初の方は大人しかったリヒテルもこれに触発されたのか、長大なカデンツァからコーダに向かって、轟音のような迫力のある打鍵を炸裂させ、オーケストラと互角に張り合います。
第2楽章は一転、幻想的な雰囲気に包まれ、リヒテルの叙情的なピアノが魅力満点です。
続く終楽章もシューマンやブラームスの協奏曲と錯覚するような渋めの音楽ですが、ロンドの軽快さを壊さないギリギリのところで落ち着いた堅実な演奏を両者とも展開します。爆発的なパッションを期待していた聴き手はがっかりするかもしれませんが、この曲をピアノ付きの交響曲ととらえていた作曲家の想いをしっかり表現した音楽になっていると思います。
マゼール、マタチッチとの手に汗握る競演
このボックスの中でちょっと意外だったのが、マゼールと共演したブラームスの「ピアノ協奏曲第2番」の凄さです。
日頃、この曲の名盤として採り上げられることが少ないディスクなのに、あまりにも素晴らしい完成度だったので、ここで感想を述べることにしました。
冒頭からものすごいエネルギーの爆発で、我々が想像するリヒテルのあのピアノの音が鳴り響きます。すると、指揮者のマゼールが伴奏に徹するどころか、パリ管弦楽団からミュンシュ時代のような激しい音楽を引き出し、強烈なピアノに一歩も引きません。その激しさは、前項のクライバーを上回るほどです。
第2楽章もドラマティック。よく言われる「マドンナの宝石」に似たイ短調の主題が何と切なく美しく響くこと。それをマゼールが、20代の頃の熱情を思い出したかの如く、何かに憑りつかれたような激情的な音楽を創り上げていきます。また、そんなオーケストラに対して微動だにせず、重心の低いテンポで圧すリヒテルの力強いピアノも圧巻です。
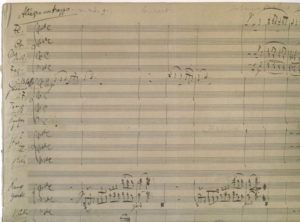
次の第3楽章は、冒頭のチェロ独奏も聴きどころですが、3部形式の第3部でピアノ、チェロ、クラリネットの3重協奏曲(ここでも!)の様相を示すところで、天上の音楽と呼ぶにふさわしい箇所が登場します。ここはぜひ聴いて頂きたいものです。
フィナーレは大変有名な旋律のオンパレード。軽快な第1主題に対し、ブラームスらしい憂愁漂う第2主題が対比されるところがたまらない魅力なのですが、マゼールは1度目はあっさりこなします。しかし、ピアノと掛け合ったり、第1主題と目まぐるしく交錯させるうちに、ボウイングなどに微細な表情を付けて、徐々に濃厚な表現を深めていきます。こういうところが、業師の本領発揮と言えるでしょう。
リヒテルのピアノは冴えた美音、力強い打鍵でありながら、テンポ、調、デュナーミクが激しく変化する難所をやすやすと乗り越え、やはり微動だにしない重心の低さで最後まで弾き切ります。オーケストラの雰囲気はかなり違いますが、ピアノだけなら往年のバックハウス、同僚のギレリスによる名盤同様、きわめてオーソドックスなスタイルと言えるでしょう。
このボックスの協奏曲篇。
他にも若いムーティと収録した溌剌としたモーツァルト、ベートーヴェン。同じマゼール&パリ管と入れたバルトークとプロコフィエフも聴きものですが、昔から決定版として知られるマタチッチとのシューマン、グリーグにも触れておきましょう。
ロヴロ・フォン・マタチッチ(1899年 – 1985年)はユーゴスラビアの指揮者ですが、とりわけわが国ではNHK交響楽団との共演で、大変な人気がありました。しかし、欧米ではいわゆるカペルマイスター的扱いで華々しいスターダムには程遠く、仕事にも事欠くことから、本人がN響との仕事を切望していたと言います。
そんな彼の本領は豪快なワーグナーとブルックナーの指揮で発揮され、特に後者の「交響曲第8番」は、N響の歴史に残る一級の演奏として崇められています。
一方、メジャーレーベルでの彼の録音は大変少ないのが現状です。チェコのスプラフォンというレーベルから、ブルックナーの7番が出ていたり、あとはウェーバーの歌劇「魔弾の射手」、レハールの喜歌劇「メリー・ウィドウ」のふたつの名盤が知られている程度です。
そんな彼が、伴奏者としての腕前を披露したのがリヒテルとのシューマンとグリーグ。どちらも冒頭が有名で似通っていますが、演奏がパッとしないと、いわゆる“出オチ”の曲になりかねません。
しかし、そんなことは杞憂と笑い飛ばすばかりに、リヒテルとマタチッチは雄大な音楽を構築していきます。ロマンティックで独特の憂愁が漂い、明るい部分は南ドイツの日差しを感じさせるような豪快なスケール。これらは望み得る最高の演奏を成し遂げていると言って良いでしょう。